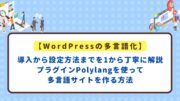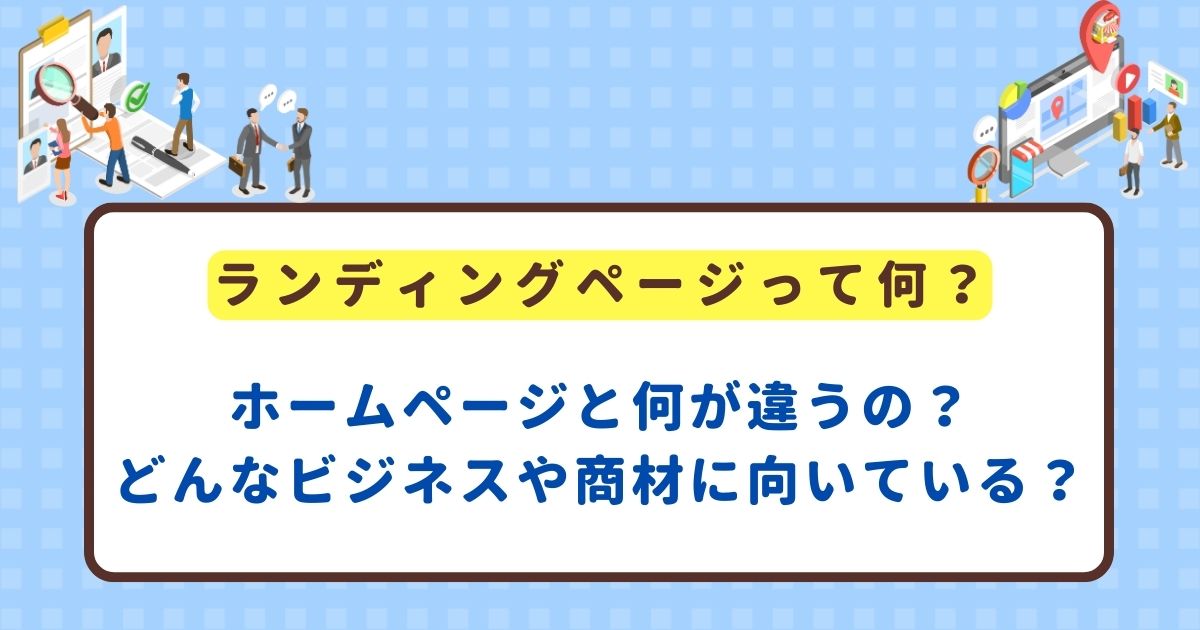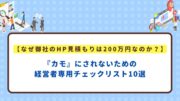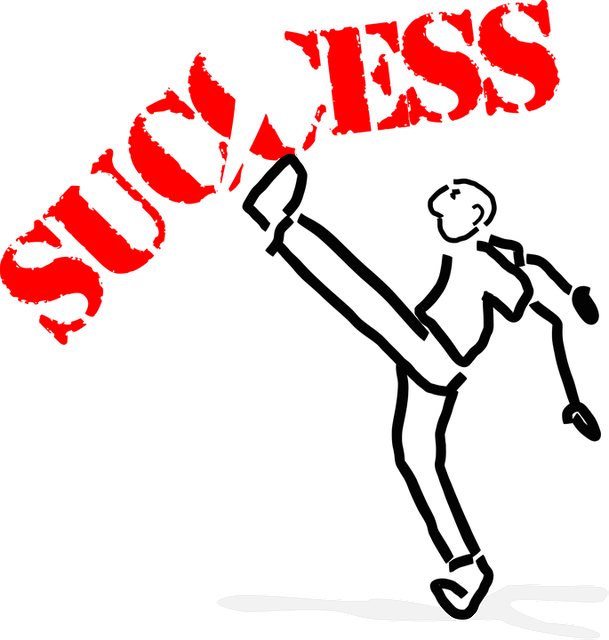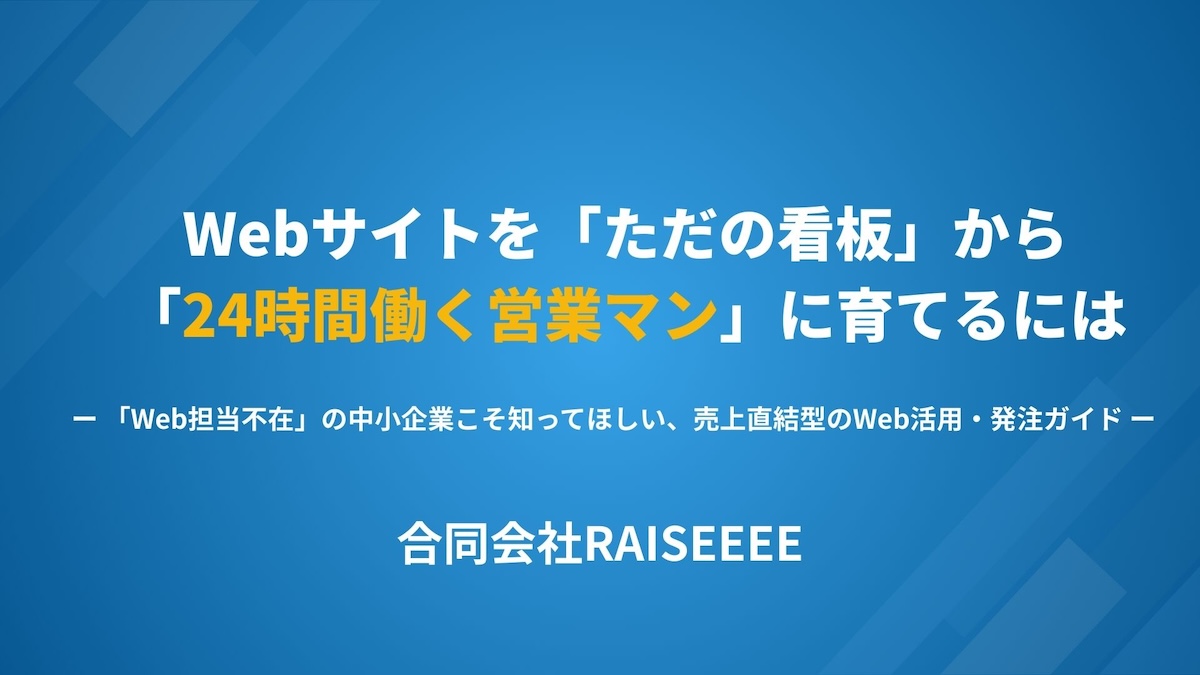【保存版】ホームページ制作前に必ず確認すべき12のチェック項目
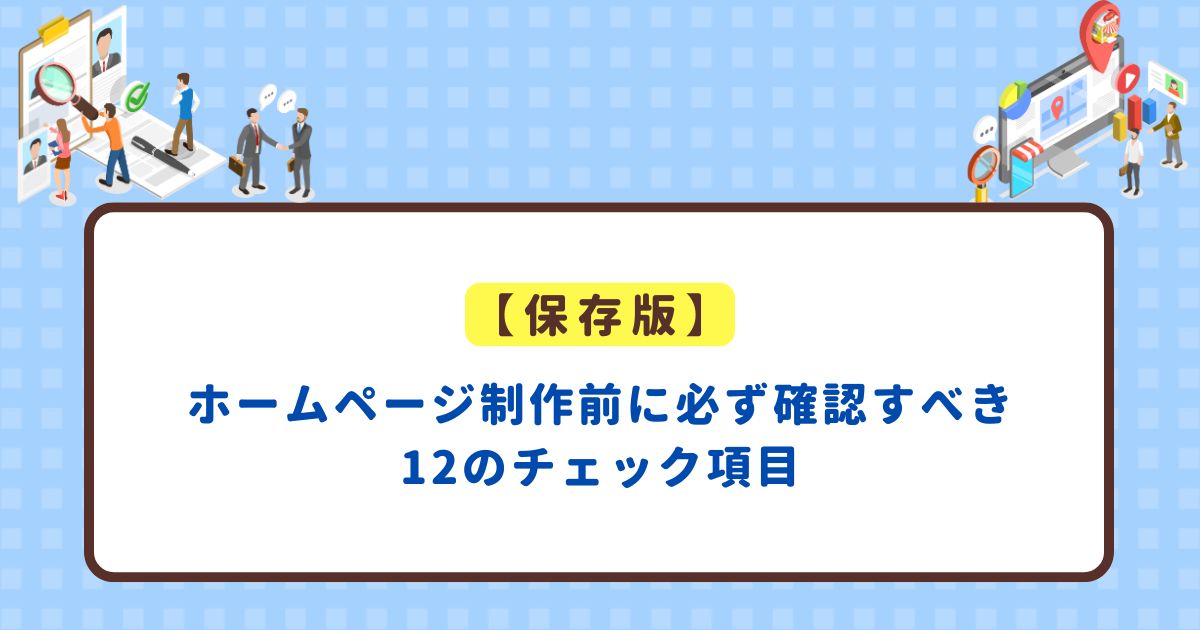
ホームページを制作する際、外注をする場合でも、自分で作る場合でも、準備を怠り、なんとなくで作ってしまうと高確率で失敗をします。
せっかく多くの時間とコストをかけてホームページを作るのであれば、期待している成果が出せるものにしたいところ。
そのためには、制作前の事前準備でほとんど決まる、といっても過言ではありません。
今回は、初めてホームページを作る方や、リニューアルを検討している方向けに、制作前に必ず確認しておきたい12の項目をチェックリスト形式で解説します。
今回ご紹介する内容をしっかり実践していただければ、ホームページを作る際に失敗をする確率をぐっと下げることができるでしょう。
チェックリスト:ホームページ制作前に確認すべき12項目
ホームページ制作を依頼する前にチェックすべき項目には、以下の12点が挙げられます。
- ホームページの目的を明確にする
- 成果目標(KGI・KPI)を設定する
- ターゲットとペルソナを明確にする
- 自社や商品の強みを整理する
- 競合サイトの分析
- 参考にしたいデザインや機能をまとめる
- ページ構成と必要コンテンツを決める
- 素材(写真・ロゴ・動画等)の準備状況を確認する
- 制作予算と運用費を明確にする
- 納期とスケジュール感を決める
- 公開後の運用方針と担当者を決める
- 制作会社選びの基準を設定する
1. ホームページの目的を明確にする
まずは、ホームページを作る「目的」をはっきりさせましょう。
「そんなことは当たり前」と感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、私の経験上、ここが案外ふわっとしているケースが非常に多くあります。
目的があいまいなまま進めると、方向性がブレて「誰のためのサイトなのか」がぼやけ、完成したときには見た目はきれいでも成果が出ない――そんな残念な結果になりかねません。
ホームページ制作は家づくりに似ています。
設計図(=目的)がなければ、立派な材料を集めても理想の家は建ちません。
だからこそ、一番最初に時間をかけて目的を言語化することが、成功の第一歩なのです。
たとえば、目的が「新規顧客の獲得」であれば、ホームページは単なる会社案内ではなく、見込み客を行動に導く営業ツールとして設計する必要があります。
たとえば、
- トップページでキャッチコピーや強みを端的に打ち出す
- 詳細ページで実績やお客様の声を掲載し、信頼を補強する
- 問い合わせボタンや資料請求フォームをページ下だけでなく要所にも配置し、「今すぐ行動できる環境」を整える
などが必要になってくることがわかります。
もしこの目的を意識せず、会社概要や沿革ばかりを前面に出してしまうと、訪問者は「この会社は何をしてくれるのか」がわからず離脱してしまいます。
目的が明確かどうかで、見込み顧客がアクションを起こしてくれるかどうかの確率が大きく変わるのです。
2. 成果目標(KGI・KPI)を設定する
目的を決めたら、次は「どの程度成果が出れば成功といえるのか」を明確にする必要があります。
「なんとなくアクセスが増えた」「良いサイトができた気がする」――これでは成果を測れず、改善のしようもありません。
そこで重要になるのが KGI(最終目標)とKPI(中間指標) です。
- KGI(Key Goal Indicator)=最終的に達成したいゴール
例:月間問い合わせ件数10件、新規売上30%アップ、採用応募5件 など - KPI(Key Performance Indicator)=ゴールに至るまでの途中経過の目印
例:月間アクセス数3,000PV、資料請求率3%、ブログ記事月4本更新 など
たとえば目的が「新規顧客の獲得」なら
- KGI:月間問い合わせ件数10件を達成する
- KPI:アクセス数を増やす、滞在時間を伸ばす、資料請求率を上げる
といった形で設定できます。
これがあると「今どの段階まで来ているのか」「改善すべきは集客か、コンテンツか、導線か」と判断できるようになります。
逆に数値目標を持たずに公開すると、アクセスが伸びても「それで結局、売上はどうなの?」という肝心な問いに答えられなくなります。
ホームページ制作はマラソンに似ています。
ゴール(KGI)が見えているからこそ、途中のチェックポイント(KPI)を確認しながら走れるのです。
ゴールがなければ、どれだけ走っても「正しい方向に進んでいるのか」すらわかりません。
目的を数値に落とし込むことが、成果を出すための出発点になります。
3. ターゲットとペルソナを明確にする
ホームページを誰に向けて作るのかを決めることは、目的と同じくらい大切です。
ここがあいまいだと「誰にも響かない、ただ情報を並べただけのサイト」になりがちです。
まずはターゲットを設定しましょう。
ターゲットとは「年齢・性別・職業・地域」といった属性のことです。
さらに一歩踏み込み、よりリアルな人物像を描いたものがペルソナです。
ペルソナ例
- 年齢:35歳
- 職業:中小企業の経営者
- 課題:自社の集客がWebでうまくできていない
- 行動:SNSはあまり使わず、Google検索で情報収集
上記の例はかなりざっくりとしたペルソナにはなりますが、ペルソナを具体化すると、「その人がどんな言葉に反応しやすいか」「どんなデザインなら安心できるか」が見えやすくなります。
たとえば、同じ「美容室のサイト」でも、
- 20代女性がターゲットなら → 流行を取り入れたデザインやSNSとの連動が効果的
- 50代以上がターゲットなら → 落ち着いた配色と、料金・アクセスのわかりやすさを重視
このように、ターゲット次第でホームページの構成もデザインも大きく変わります。
逆に、ターゲットやペルソナを定めずに制作を始めると、「結局このサイトは誰に向けたものなのか?」が伝わらず、訪問者の心に残らないサイトになってしまいます。
だからこそ、制作前に「具体的に誰に届けたいのか」を明確にすることが、成果の出るホームページづくりの前提条件なのです。
4. 自社や商品の強みを整理する
ホームページで成果を出すためには、デザインの美しさ以上に「自社が選ばれる理由」を明確にすることが重要です。
どんなに見た目が整っていても、強みが伝わらなければ「結局この会社は他とどう違うの?」と訪問者に思われ、比較検討の中で埋もれてしまいます。
以下のようにこれらを整理しておくと、ホームページのコピーやデザインに落とし込みやすくなります。
- 他社にはない特徴や価値 →「地域密着で即日対応」「女性スタッフのみで安心」「完全オーダーメイド対応」
- 実績や事例 → 「年間施工数300件」「導入後売上150%アップの事例あり」
- お客様の声や受賞歴 → 「お客様満足度92%」「業界アワード受賞」
強みが整理されていないと、制作の現場では「とりあえずサービス紹介を並べるだけ」になりがちです。
その結果、きれいなサイトはできても、訪問者の心には刺さらず、最終的な問い合わせや購入につながらないという事態に陥ります。
強みは単に「うちのサービスは質が高いです」と抽象的に語るのではなく、数字や実績で裏付けることが大切です。
例えば、「質が高い」ではなく「リピート率85%」「創業20年で累計◯◯件」など、客観的なデータがあるだけで説得力は大きく変わります。
5. 競合サイトの分析
ホームページ制作を成功させるためには、競合がどんなサイトを運営しているかを把握することが欠かせません。
なぜなら、訪問者は自社サイトだけを見るのではなく、必ず複数のサイトを比較してから選ぶからです。
まずは、狙いたいキーワードで検索し、上位表示されている競合サイトを3〜5つピックアップしましょう。
そのうえで、以下のポイントをチェックします。
- デザインや色使い
(高級感があるのか、親しみやすいのか) - 情報の見せ方
(文章中心か、写真や動画を多用しているか) - キャッチコピー
(最初に何を一番伝えたいと思っているのか) - 導線設計
(問い合わせ・購入・予約までの流れがスムーズか)
これらを比較すると、「業界で求められている表現」と「まだ誰も取り組んでいない空白領域」の両方が見えてきます。
競合を調べずに制作を進めると、
「気づいたら他社と似たようなサイトになってしまった」
「差別化できず、選ばれる理由が伝わらない」
といった失敗につながります。
せっかく投資して作ったホームページが、競合の陰に埋もれてしまうのは非常にもったいないことです。
競合分析の目的は「そのまま真似すること」ではありません。
- 良い部分は参考にする
- 弱点は自社で強みに変える
この2つを意識することで、他社との差別化が自然と浮かび上がってきます。
競合サイトの分析は「勝てる戦い方を見つけるためのリサーチ」です。時間をかけてでも取り組む価値のある工程といえるでしょう。
6. 参考にしたいデザインや機能をまとめる
制作会社に「こんな雰囲気でお願いします」と口頭で伝えるだけでは、人によって解釈が異なり、イメージのズレが起きがちです。
結果として「思っていた仕上がりと違う…」というトラブルにつながることも少なくありません。
そこで効果的なのが、参考になるサイトのURLやスクリーンショットをあらかじめ用意して共有することです。
色やレイアウト、写真の使い方など、具体的に示すことで制作会社とイメージを共有しやすくなります。
さらに、デザインだけでなく「どんな機能を備えたいか」もリストアップしておきましょう。
例えば以下のようなものが挙げられます。
- 予約機能(クリニックや美容室など、来店型ビジネスに必須)
- EC機能(ネットショップ運営や商品販売用)
- 会員制ページ(会員限定情報や資料ダウンロード用)
- 多言語対応(海外顧客や観光客向け)
これらを明確にしておくことで、制作側は仕様に沿った設計ができ、無駄な修正や追加費用を避けられます。
「どんなデザインにしたいか」「どんな機能が必要か」を事前にまとめておくことは、制作の精度を高め、完成後の満足度を大きく左右する準備作業なのです。
7. ページ構成と必要コンテンツを決める
ホームページ制作をスムーズに進めるためには、まずどんなページを用意するのかを事前に決めておくことが大切です。
ページ構成が曖昧なままでは「とりあえず作りながら考える」状態になり、途中で迷走したり、納期が延びたりする原因になります。
一般的な企業サイトでよく用意されるページは次のとおりです。
- トップページ
- サービス紹介
- 料金表
- 会社概要
- ブログ・お知らせ
- お問い合わせ
これらを決めたら、さらにページごとに必要なコンテンツをリスト化しましょう。
- サービス紹介ページ:サービスの特徴、他社との違い、事例
- 料金ページ:料金プラン、注意点、割引制度
- 会社概要ページ:代表挨拶、沿革、アクセスマップ、スタッフ写真
事前に文章や写真の準備が整っていれば、制作途中で「このページに何を載せるんだっけ?」と手が止まることもありません。
逆に準備不足のまま着手すると、制作が中断してスケジュール全体が遅れる大きな原因になります。
8. 素材(写真・ロゴ・動画等)の準備状況を確認する
写真やロゴといった素材のクオリティーは、ホームページの印象に大きく影響します。
どんなに優れたデザインでも、画像が低解像度だったりすると、全体の完成度が一気に下がってしまいます。
制作前に、次のような素材が揃っているかを確認しておきましょう。
- 写真:プロカメラマンに依頼するか、自社で撮影するか。店舗や人物、商品写真は特に重要。
- ロゴ・ブランドカラー:AIデータやPNGなど、Webで扱いやすいデータ形式で用意できているか。
- 動画:サービス紹介や採用ページなどで動画が必要かどうかを検討。
これらが準備できていないと、制作の進行が遅れるだけでなく、完成したサイトの印象も「素人っぽい」と見られてしまうリスクがあります。
9. 制作予算と運用費を明確にする
ホームページ制作でよくある失敗のひとつが、「制作費だけを見て安心してしまうこと」です。
ホームページは公開して終わりではなく、サーバーやドメインの更新、セキュリティ対策や保守など、運用にかかるランニングコストが必ず発生します。
費用は大きく分けて次の2種類です。
- 初期費用:制作費、写真撮影費、ライティング費など
- 運用費:サーバー代、ドメイン更新費、保守・メンテナンス費など
さらに、追加費用が発生するケースも少なくありません。
たとえば「途中で仕様を変更したい」「有料の写真素材を使いたい」といった場合です。
これらを事前に確認していないと、完成後に「思った以上にお金がかかる」という事態に陥りがちです。
だからこそ、予算は初期費用+運用費+追加費用の可能性まで含めて考えることが大切です。
そのうえで、予算の上限と下限を決め、制作会社と共有しておくとスムーズに話が進みます。
10. 納期とスケジュール感を決める
ホームページの公開時期を決めるときに、よくやってしまうのが「なるべく早くお願いします」という依頼の仕方です。
しかしこれでは制作会社も優先度をつけられず、結果として後回しになったり、無理なスケジュールで質が落ちたりすることがあります。
大切なのは、具体的な公開希望日を設定することです。
たとえば「◯月◯日から新商品を発売するので、その前に公開したい」といったようにイベントや事業計画と連動させると、制作側も逆算してスケジュールを立てやすくなります。
また、納期を決める際には「いつまでに何を決めるか」まで落とし込むことが重要です。
- ◯月◯日までに原稿を提出
- ◯月◯日までにデザイン確認
- ◯月◯日にテスト公開
このように細かくマイルストーンを設定しておくと、制作が滞りなく進み、余裕を持って公開を迎えられます。
11. 公開後の運用方針と担当者を決める
ホームページは公開した瞬間がゴールではなく、そこからが本当のスタートです。
検索順位を上げたり、問い合わせを増やしたりするには、定期的な更新や分析、改善を継続する体制が欠かせません。
そのために、制作前から「公開後は誰がどのように運用するのか」を決めておきましょう。
- 誰が更新作業を行うのか(自社で担当するのか、制作会社に依頼するのか)
- SEOや広告運用を取り入れるか(集客の手段をどこまで行うのか)
- SNSとどのように連動させるか(記事更新をSNSにシェアする、キャンペーンと連動させる など)
このとき重要なのは、担当者の業務量も考慮することです。
普段の業務に加えてサイト更新を担う場合、無理が生じると更新が滞り、せっかくのホームページが放置されてしまいます。
「どのくらいの頻度で更新するのか」「外部に任せる部分はどこまでか」を最初に明確にしておけば、運用が継続しやすく、ホームページを育てていく基盤が整います。
12. 制作会社選びの基準を設定する
同じ「ホームページ制作会社」といっても、得意分野やサポート体制は大きく異なります。
デザインに強い会社もあれば、マーケティングやSEOに特化している会社もあり、依頼する側の目的と合わなければ満足のいく成果は得られません。
だからこそ、制作会社をどんな基準で選ぶかを事前に明確にしておくことが重要です。
選定の際にチェックすべきポイントは次のとおりです。
- 実績や専門分野:自社と同じ業界・規模のサイトを作った経験があるか
- コミュニケーションのしやすさ:専門用語をわかりやすく説明してくれるか、対応は丁寧か
- 提案力:依頼を受け身でこなすだけでなく、改善提案や新しいアイデアを出してくれるか
- 契約条件:著作権の扱い、納品データの範囲、更新の自由度などに不利な条件がないか
これらを確認せずに費用だけで選んでしまうと、完成後に「思ったように運用できない」「追加費用ばかりかかる」といったトラブルにつながりかねません。
一方で、自社の目的や体制を理解し、長期的に伴走してくれるパートナーを選べば、ホームページは単なる制作物にとどまらず、ビジネスを伸ばし続ける強力な武器になります。
まとめ
ホームページ制作は、事前準備の段階で成功の8割が決まるといっても過言ではありません。
今回ご紹介した12の項目を事前に整理しておけば、制作の進行がスムーズになるだけでなく、「成果につながるホームページ」を実現できます。
とはいえ、日々の業務をこなしながらこれらを一つひとつ準備するのは簡単なことではありません。
もしこの記事を読んで「大事なのは分かるけど、うちでは手が回らない…」と感じた方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。
貴社の目的や予算、体制に合わせて、最適なホームページ制作プランをご提案し、公開後の運用まで伴走いたします。